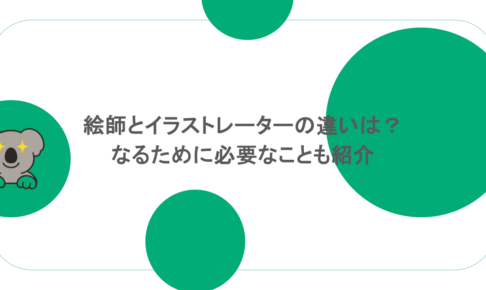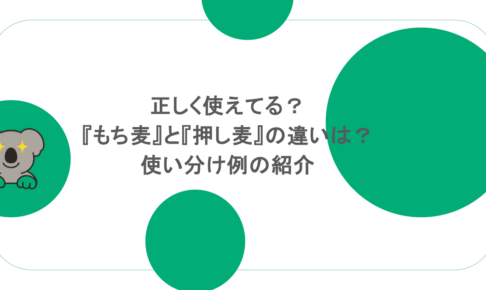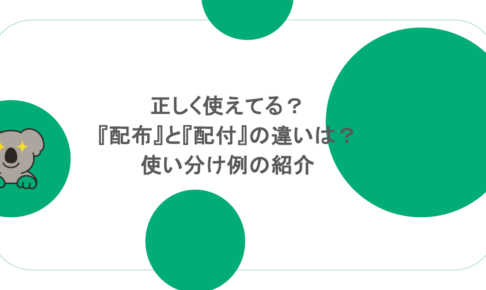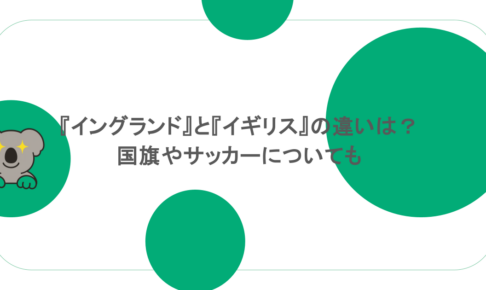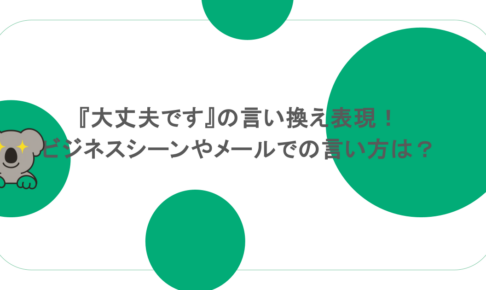日本人の暮らしの中で、馴染みのある神社とお寺ですが、両者の違いや正しい使い方をご存知でしょうか?参拝方法の違いや、願い事はどちらにするのかなど、1度は悩んだ経験がある人もいるようですね。
そこで今回は、神社とお寺の違いや特徴、行事・祈願の使い分け例について調査しましたので皆さんにご紹介していきます。
このページの目次
神社とお寺の違いや特徴を紹介
似ているようで異なる神社とお寺について、それぞれの違いや特徴を紹介します。
参拝方法が違う
信仰する宗教が神道と仏教で異なることにより参拝方法が変わってきます。お賽銭を奉納した後に2回礼をして、手を2回叩いて再度礼をする「二礼二拍手一礼」が基本となるのが神社の参拝方法と言えます。
一方でお寺は、お賽銭を奉納した後に胸の前で両手を合わせて合掌し、拍手を打たないのが作法。それぞれの作法を知ることで、より丁寧な参拝が可能です。
願望が違う
神社では「現世での幸せ」、お寺では「死後の安らぎ」や「現世での苦しみからの救い」を願う点が異なります。神社への参拝は穢れを清めるための方法であり、「心機一転の決意表明」との意味を持つため、自分に都合の良いことだけを願うのは本来の主旨からはずれるようです。
一方でお寺は、祀られている仏様により現世か死後かに分かれます。お寺では「願う」というより、自分の環境や生活を良いものにしていく「誓い」を立てる意味合いが強いでしょう。
聖職者が違う
聖職者が異なる神社とお寺。神社に仕えるのが「神職」で「神主」として親しまれており、お寺にいるのが、「僧」と呼ばれる仏教の修行者です。神社では神主が神様に奉仕し、祭祀や祈祷・社務などを担当します。神道には説教がないため仏教のように教えを説くことはなく、巫女は神職を補佐して神楽や奉仕を担うようです。
一方でお寺では僧が法要や説法・お経を読み、寺や墓地も管理。寺を任される僧は「住職」・教えを説く僧は「和尚」・女性の僧は「尼」と呼ばれ、仏事に携わっています。
建物が違う
神様が祀られている神社と、仏像が祀られるお寺の違いは建物です。神社は入口に「鳥居」が立ち、参道を進むと「手水舎」で身を清めて「本殿」へ向かいます。ご神体は神の宿る存在として、人目に触れないように大切に祀られているのが特徴です。
一方でお寺の建物は「伽藍」と「僧房」に分かれており、仏像を祀る礼拝施設と僧侶が生活する場所が含まれます。もともとは僧の修行場でしたが、仏像や仏塔が整備されて現在の形になりました。一般的に「山門」から入って「金堂」や「塔」が並ぶ構造で、仏像を間近に拝めます。
神社とお寺の特徴は?
参拝方法や聖職者が異なる神社とお寺ですが、両者の特徴について1つずつ見ていきましょう。
神社とは?
日本の伝統的な宗教「神道」の信仰の場が神社です。古くから日本人は山や海などの自然に魂が宿ると考えて、参拝する文化を築いてきました。この考え方から「八百万の神」と呼ばれる多くの神々を信仰するようになったようです。
神々が宿る場所を神聖な祭場として設け、やがて雨風を防ぐための建物が建てられ、現在の神社へと発展しました。また、神社は規模や格式によって「神宮」「宮」「大社」「社」「大神宮」などの名称で区別されています。
お寺とは?
世界三大宗教の1つ「仏教」を信仰し、修行や学びの場として建てられた場所がお寺です。仏教は紀元前6〜5世紀頃、インドで釈迦が悟りを開き、その教えを弟子たちに伝えたことから始まりました。釈迦の教えは中国や朝鮮半島を経て日本に伝わり、独自の文化や信仰と結びつきながら広まったとされています。
お寺は僧侶たちが仏教の教義を学び、修行を積む場所であると同時に、地域の人々の心のよりどころとしての役割も果たしてきました。仏像を安置して法要や供養が行われ、仏教の教えを日常生活に根付かせる場として親しまれています。
神社とお寺を利用する際の行事や祈願の使い分け例は?
さまざまな行事や祈願がありますが、神社とお寺の使い分けについて紹介しましょう。
神社で行う行事や祈願
人生の節目や日常の願い事に合わせた行事や祈願が行われる神社。例えば、新年に1年の無事を祈る「初詣」・子供の誕生や成長を祝う「安産祈願」や「お宮参り」・子供の健やかな成長を願う「七五三」などがあります。また、災いを払う「厄除け・厄払い」や、事故を防ぐ「交通安全祈願」・建築の安全を願う「地鎮祭」や「上棟式」も重要な神社の行事です。
さらに、商売の繁盛や豊作を祈る「商売繁盛・五穀豊穣」、良縁を願う「縁結び・恋愛成就」なども行われています。これらは、日本の伝統的な神道行事に由来するものが多いようです。
お寺で行う行事や祈願
仏教の教えに基づき、先祖や故人の供養を中心とした行事や祈願が行われるお寺。春と秋のお彼岸やお盆には、先祖を偲び供養することが一般的です。また、故人の冥福を祈る法事や法要、亡くなった方を極楽浄土へ送り出す葬儀も重要な儀式と言えます。
さらに、亡くなった子供の供養「水子供養」を行うこともあり、病気の平癒や学業成就などを願う祈祷やお守りの授与も寺院の役割です。年末には「除夜の鐘」をつき、1年の煩悩を払い清める風習も広く親しまれています。
神社とお寺を利用するうえで厳格な決まりはない
神社とお寺の使い分けについての内容は一般的な傾向であり、地域の風習や家族の信仰によって異なる場合もあるため、両者を利用するうえで厳格な決まりはないようです。「家族みんなで参拝したい」や「普段からお世話になっている」などの理由で、お寺で行う祈願を神社でする人もいます。
大切なのは形式よりも気持ちであり、迷った場合は近くの神社やお寺に相談すると良いでしょう。
まとめ
今回の記事では、日本の生活で馴染みのある神社とお寺の違いを中心に、特徴や行事・祈願の使い分け例について紹介しました。
行事や祈願による神社とお寺の使い分けについて、厳格な決まりはありませんが、人それぞれの気持ちが重要なようですね。両者の違いを十分に理解し、自分に合った使い方で利用しましょう!
あわせて読みたい:稲荷神社に行ってはいけない人とはどんな人?怖いと言われる理由も調査